技術・技能
注目記事

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.5
2025.06.01
図に模式的に示す多管式熱交換器(以下熱交と略す)は、化学プラントで多く用いられるタイプの熱交である。熱交を設計する場合に、腐食性のある流体をシェル側に流すことは、原則として避ける必要がある。すなわち多管式熱交では「腐食性流体はチューブ側に流す」を原則とする。それは、図に示すように、シェル側に腐食性流体を流すと、バッフル近傍や管板近傍で滞留部が生じるため、流体の流れを均一に一定以上の速度で流すことが不可能であり、かつ伝熱管表面の付着物や腐食生成物を定期修理時などで物理的に洗浄することが困難であり、更に腐食が発生した場合の非破壊的な検査が管内側に流体を流す場合に比べ困難になるためである。 これは、伝熱管が炭素鋼の場合も、ステンレス鋼の場合も同様である。 プロセス流体に腐食性が無い場合は、冷却水は炭素鋼やステンレス鋼に対して腐食性があるため、これをシェル側に流さず管内側に流した方が、以上の種々の課題に対応する上で望ましい。このような設計段階での配慮が、熱交の信頼性やメンテナンスの負荷に大きく影響する。ただし、プロセス側流体にも腐食性が有る場合や、プロセス側流体に重合やスケーリングの発生がある場合には、それらの流体をチューブ側に流さざる得ないため、冷却水をシェル側に流す場合もあり得る。その場合は、熱交のタイプを固定管板式からU字管式や遊動頭式などのチューブバンドルを開放できるタイプへ変更し、洗浄や検査を行い易くすることが考えられる。また、冷却水側からの腐食を抑制するため伝熱管の材料を炭素鋼からステンレス鋼へ変更や、ステンレス鋼でも冷却水側からの応力腐食割れの発生を抑制するためSUS304などのオーステナイト系ステンレス鋼から、SUS329などの2相系ステンレス鋼へ変更するなど、材料面からの腐食抑制策を選択することを行うことが妥当な場合もある。

第2回 玉掛けの力学(その2)
2025.05.01
国立大学法人 九州工業大学支援研究員・客員教授堀田 源治

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.1
2025.04.01
鋼製ボルトは「強度が高いほど締結の信頼性が高い」と考えられがちである。しかし、実はそうでない場合もある。例えば、大気中や水溶液中で1,200MPaを超える高強度のボルトを用いると、使用中に軽度の腐食が発生するととともに、同時に水素を吸収して脆化し、最終的なボルトの破断に至る場合がある。 これは、図に示すように、材料の強度が高いほど水素脆化感受性が高いためである。この理由は、強度が高いほど応力集中部(ボルトの場合にねじ底)に高い応力を受けることになり、その応力集中部に吸収した水素が拡散により集中し、脆化するためである。 また、使用環境により吸収される水素量は変化し、大気中での腐食では、図中に示すように鋼材に1ppm程度まで水素を吸収する可能性があるとされている。水素脆化によるボルトの破断を防止するためには、基本的により強度の低い鋼材を選定することが妥当である。経験的に、強度1,000MPa以下の鋼材の使用が大気中では妥当とされている。 なお、鋼材の腐食を抑制するために犠牲陽極作用を期待して、亜鉛粉を含む塗料(ジンクリッチペイント)を採用することは、かえって鋼材の水素吸収を加速する可能性が高く、避ける必要がある。

第2回 潤滑油の組成
2025.05.01
RMFジャパン株式会社久藤 樹
記事一覧

サステナブルなモノづくりのために No.99
2025.06.02

第3回 玉掛けの力学(その3)
2025.06.02

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.5
2025.06.01 FREE

第147回「コンピュータの乱数 と 乱数の再現性」
2025.06.01
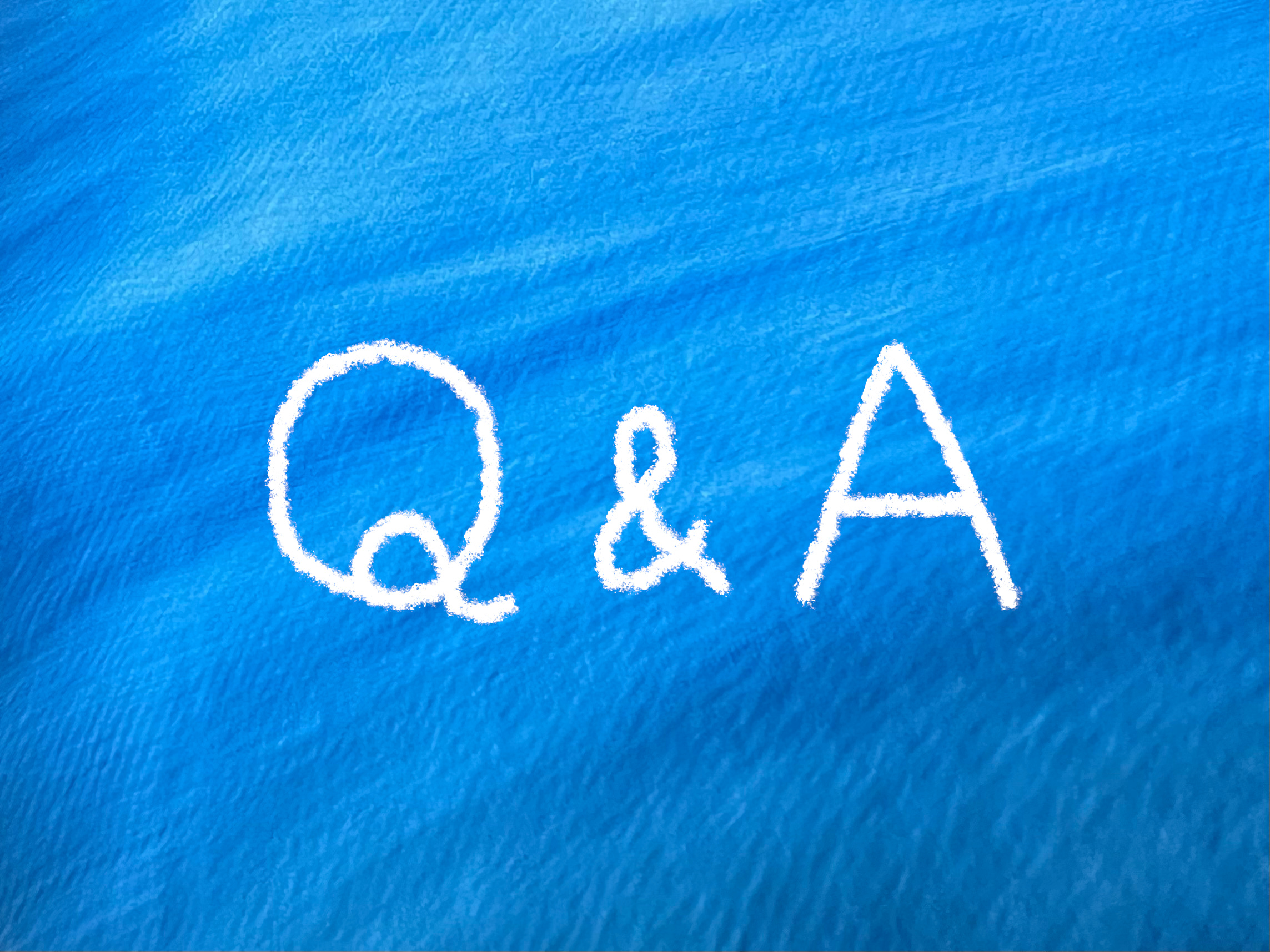
せつびさんとカンリさんの「モノづくり品質の基本のキ」#2 なぜ、「コンプライアンス不正」は起こるの?
2025.05.15

第2回 玉掛けの力学(その2)
2025.05.01

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.3
2025.05.01

第146回「シャッフルされた学生番号とハッシュ」
2025.05.01

第2回 潤滑油の組成
2025.05.01

サステナブルなモノづくりのために No.98
2025.05.01

装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.2
2025.04.15
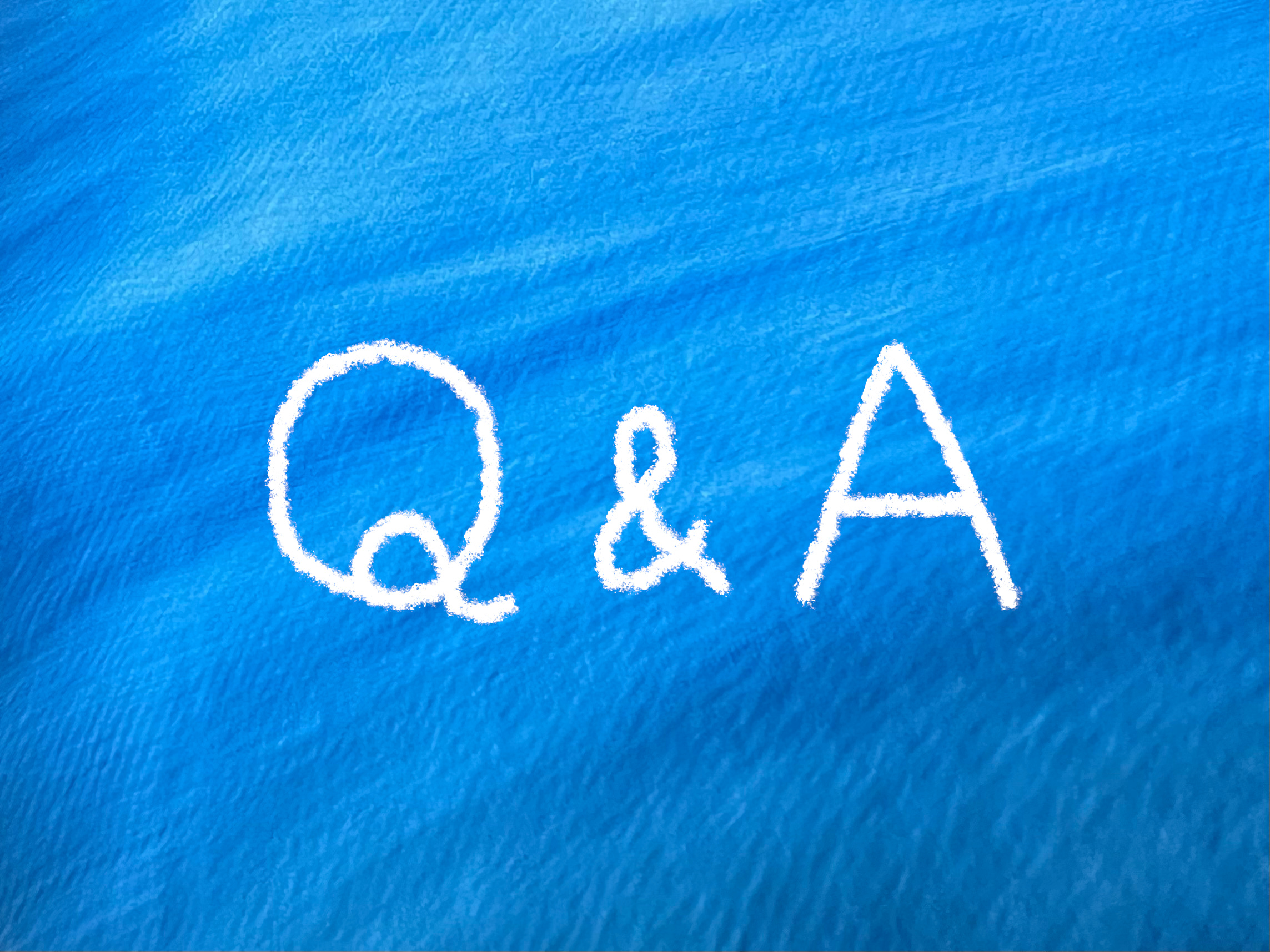
せつびさんとカンリさんの「モノづくり品質の基本のキ」#1 品質ってなぁに?
2025.04.15 無料会員
