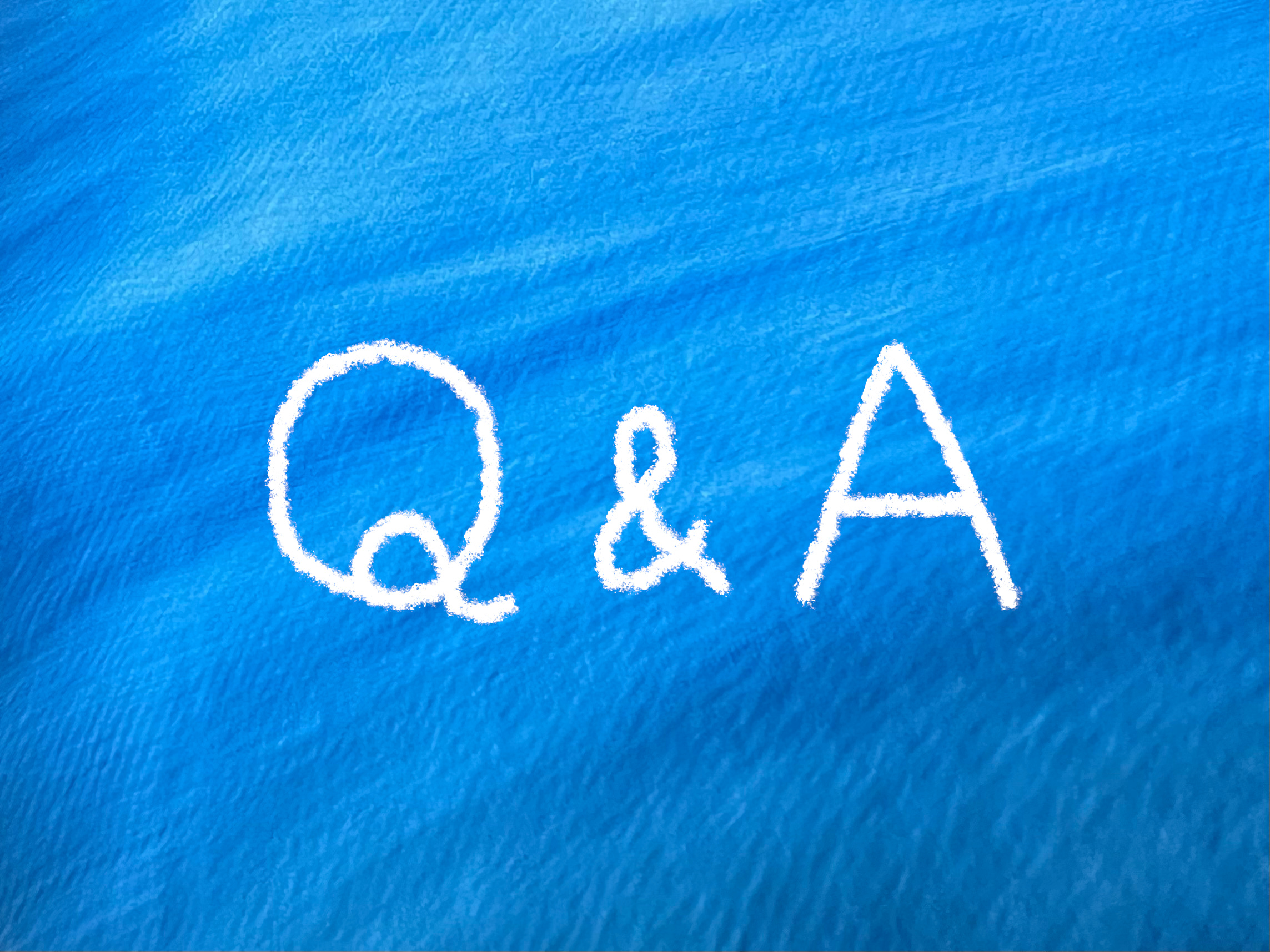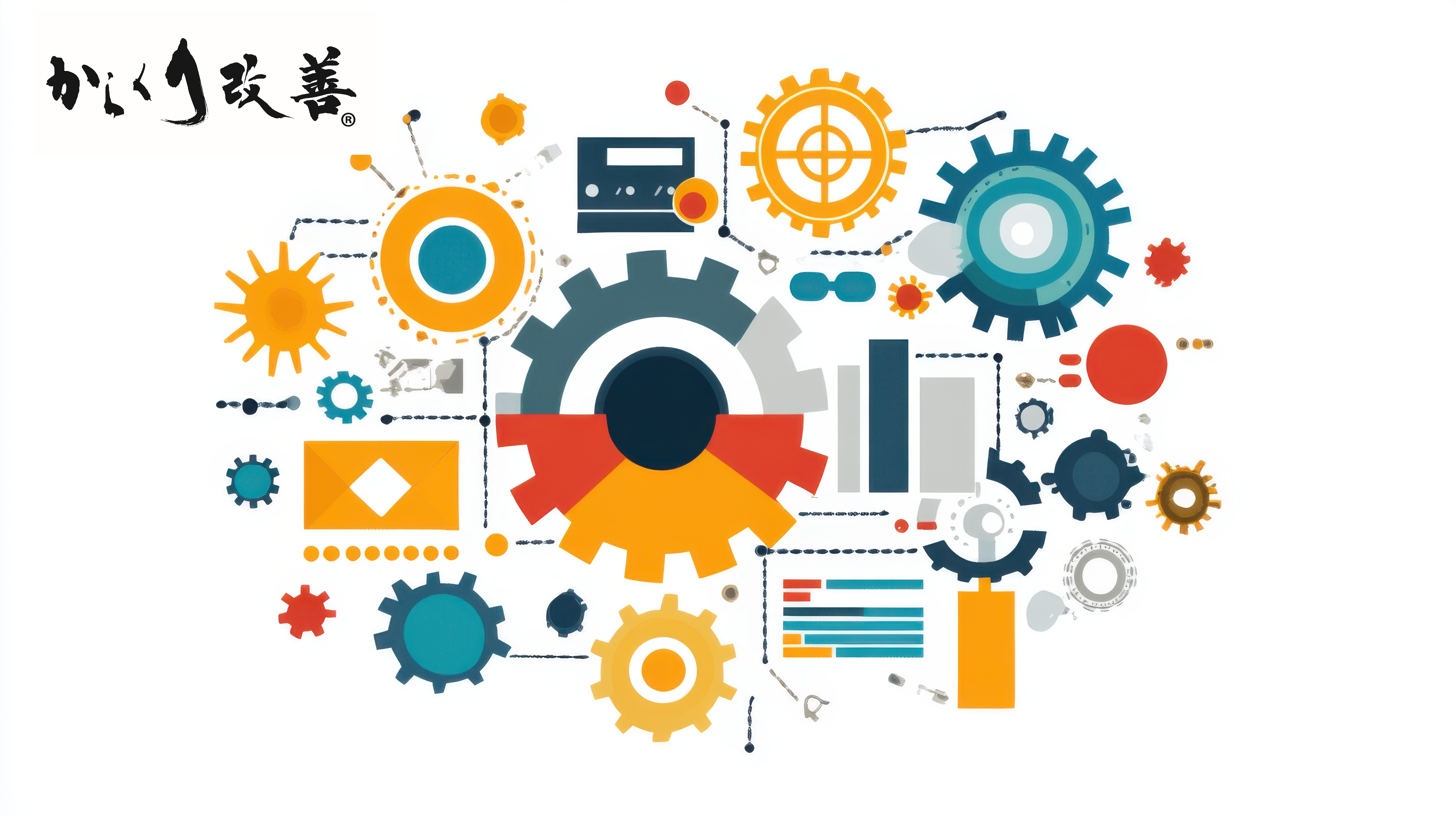装置材料の損傷・劣化「べからず集」Vol.5
2025.06.01
図に模式的に示す多管式熱交換器(以下熱交と略す)は、化学プラントで多く用いられるタイプの熱交である。熱交を設計する場合に、腐食性のある流体をシェル側に流すことは、原則として避ける必要がある。すなわち多管式熱交では「腐食性流体はチューブ側に流す」を原則とする。それは、図に示すように、シェル側に腐食性流体を流すと、バッフル近傍や管板近傍で滞留部が生じるため、流体の流れを均一に一定以上の速度で流すことが不可能であり、かつ伝熱管表面の付着物や腐食生成物を定期修理時などで物理的に洗浄することが困難であり、更に腐食が発生した場合の非破壊的な検査が管内側に流体を流す場合に比べ困難になるためである。 これは、伝熱管が炭素鋼の場合も、ステンレス鋼の場合も同様である。 プロセス流体に腐食性が無い場合は、冷却水は炭素鋼やステンレス鋼に対して腐食性があるため、これをシェル側に流さず管内側に流した方が、以上の種々の課題に対応する上で望ましい。このような設計段階での配慮が、熱交の信頼性やメンテナンスの負荷に大きく影響する。ただし、プロセス側流体にも腐食性が有る場合や、プロセス側流体に重合やスケーリングの発生がある場合には、それらの流体をチューブ側に流さざる得ないため、冷却水をシェル側に流す場合もあり得る。その場合は、熱交のタイプを固定管板式からU字管式や遊動頭式などのチューブバンドルを開放できるタイプへ変更し、洗浄や検査を行い易くすることが考えられる。また、冷却水側からの腐食を抑制するため伝熱管の材料を炭素鋼からステンレス鋼へ変更や、ステンレス鋼でも冷却水側からの応力腐食割れの発生を抑制するためSUS304などのオーステナイト系ステンレス鋼から、SUS329などの2相系ステンレス鋼へ変更するなど、材料面からの腐食抑制策を選択することを行うことが妥当な場合もある。

ものづくり屋視点による労働衛生の実践 No.2『 労働衛生の3管理と安全の「基本3原則」の意味を再考する』
2025.05.15
作業環境管理、作業管理、健康管理が労働衛生の3管理といわれている。衛生管理者をはじめとする現在の関係者にとっては「常識」かもしれないが、筆者が駆出しの作業環境測定士であったころは、まだこの建付けに至ってはいなかったと記憶している。国により策定される労働災害防止計画(5か年計画)があり、第1次計画が1958年にはじまっている。その記憶というのは、第5次(1978年~1982年)の時代である。「職業性疾病予防対策の積極的推進」の中に、「イ 化学物質の有害性調査制度等の積極的活用」「ロ 作業環境管理対策の推進」「ハ 健康管理対策の積極的推進」「ニ 産業医学の振興」の4項目が示され、作業管理は特筆されていない。 その後、専門家による議論や提起等(とくに輿、沼野ら図表ー1脚注)を踏まえて、第7次計画の同項目に、「イ 作業環境管理対策の徹底」「ロ 作業管理指針の作成」「ハ 特殊健康診断項目の見直し」・・・後略、という形で3管理の枠組みが整いはじめた。 想像の域において、当初は熱意ある産業医学関係者からの先行した働きかけに、周辺の研究者ら専門家が呼応し、環境状態の定量的把握の仕組みを整える段階にあった。原因特定から対策に至る生産現場への具体的的展開には、まだ距離があった感触を覚えている。しかし、最前線で労働者の有害物へのばく露(当該物質等にさらされること)を防ぐためには、生産技術の領域に踏み込むことが焦眉の課題であり、諸先輩の尽力によって、現在の形に至ったものと受け止めている。個人的にも歯痒さを覚え、労働衛生機関を飛び出して製造業の現場に転身したのは、この後である。図表ー1は、有害物質の取扱いに係る労働衛生3管理の課題と関係である。左上の原材料が有害(ハザード)であった場合、そのハザードが、生産プロセスと作業者との関わりによって、右下に向かう結果がリスクとなり、そのリスクが許容限度を超えた場合に健康障害に至る可能性が“大”となる。 作業環境管理は上流に位置する。ハザードである有害物質は、用いないか代替されることが本質であるが、最小限使用せざるを得ない場合には、設備・工程の設計や改善により、作業環境への発散や付着による作業者への接触を可能な限り抑制する必要がある。環境空気を汚染するリスクについては、局所排気装置等により低減策を講じる。 中流が作業管理となる。ここでは、上流で抑制しきれなかった残存リスクに対して、ばく露を最小限にする作業標準の設定や個人用保護具(防じん・防毒マスク、保護メガネ、保護手袋など)の着用により、人体への浸入を最終的に防護する。ここまでの段階で、原則としてリスクを許容限度以下に抑え込まなければならない。 しかし、上流~中流域での設計、維持・管理が不十分であった場合や故障、ミスオペ、あるいは化学物質等に対する感受性の極端な個人差によるリスクは“ゼロ”ではないので、健康管理の仕組みによって、フォローアップする。この最終プロセスは、決して作業者を「炭鉱のカナリア」にしてはならないのであって、ばく露に係る監視・測定のフィードバックは中流以前で行われなければならない。健康診断の所見によっては、「安全」に例えるなら災害発生と同等の意味を持つ。

第147回「コンピュータの乱数 と 乱数の再現性」
2025.06.01
わたしの旧twitter(X)にはいろいろな技術情報が流れてきます。気になったものはその情報をたどって詳細を確認するのですが、少し前に「乱数をつくる」手法が流れてきました。メカトロの専門の範囲で、また様々な目的で、乱数を使うため関心対象です。生産設備などを動かすときにランダムさは無縁そうに見えますが、ロボット分野では乱数を使う手法が様々ありますし、我々の日常でも乱数のお世話になっています。 乱数、乱数列は、文字通りランダムな数値です。それまでに出てきた数値列から、次に出る数値は予想できません。乱数を得るという作業(サイコロをふるとか、関数の実行など)のたびになにか数値を得ます。一方、一般的なコンピュータの計算にはランダムな要素がないため、コンピュータのプログラムで作り出した乱数は、乱数っぽく見えても何か規則があって、かつ非常に長い周期の繰り返しがあり、擬似乱数と呼ばれます。 擬似乱数にはいくつもの生成方法が提案され、使われています。それら方法を比較するための主な評価指標は、計算の手間と乱数としての性質の良さです。前者については、たまにしか使わないものであれば負担になりませんが、ランダムな信号の生成では使用回数が多くなりますし、ロボット制御分野にもひたすら乱数を使うような手法があり、その場合は簡単な演算で済むに超したことはありません。後者はどのくらい本来の乱数の性質に近いかという観点で、単純にはその繰り返しの周期の長さ、ある程度の数量の乱数を作った時にその列から次の値を予想し得るかどうかなどがあります。 コンピュータの乱数はちょっとしたゲームを作ろうとしたときなどにも(たとえばじゃんけんでも)必須なので、私はプログラムを作るようになった早い段階から触れていました。プログラミング言語標準の乱数ではしばしば、「0~ある上限」までの整数が一様に出てくるため、たとえば、{1,2,3}から一つ出るものが欲しいという場合は、 (得た乱数÷3の余り)+1のような計算をします。この使い方をしたときにも綺麗な乱数かという観点もあります。 あるとき、画面上で上下左右にランダムに動き回る点をつくろうとしました。4で割った余り(より正確には下位2ビットを使用)の0123で4方向を決めるプログラムを書いて実行したところ、動きません。正確には、上下左右の動きを規則的に繰り返して、小さな往復運動をしていました。当時は乱数とはランダムなもので、このような現象が起き得るという知識はなかったため、移動方向を画面に連続して表示させて現象を特定しても何が悪いのかわかりませんでした。ふと、「5で割って余り0123は移動、4は乱数出し直し」としてみたらランダムっぽく動き回ったので、そのときはそれで良しとしました。擬似乱数の方式によってはこのような問題があることを知ったのは、ずっと後のことでした。 技術全般に「いいところしかない」なら、特許等の制約がないなら、その手法が席巻するはずですが、複数が共存しているのは利点欠点の取捨選択があるためです。冒頭の、流れてきた手法は原理を理解しきれませんでしたが、小型のマイコンで動かすのにも軽そうな方法に見えました。

サステナブルなモノづくりのために No.99
2025.06.02
実はこの話題を本連載で3回目なのだが、筆者の担当する大学院の講義の1コマで「最近の若者は車を買わなくなったのか?」というテーマで学生とディスカッションをやっている。毎回新たな発見があるので、今回も学生の意見を紹介しよう。 この問いの背景は、我が国の基幹産業の大黒柱であり、大量生産・大量販売の象徴である「自動車」を、若者が購入しなくなったのだとしたら、それは、ある消費者層(この場合は若者)の消費形態が大きく変わったということだから、持続可能な社会の実現に向けて何らかの参考になるのではないか?ということを考えている。 話の前提はかなり極端で、場所は東京の真ん中で、足として車が必要な地方とは状況が大きく異なる。対照とする時代を、筆者が若者だったときの多少サバを読んで1990年と置いている。まさにバブル真っ盛りであり、大学生になったら車を買うのが当たり前、車がないとデートできない、格好良いスポーツカーを持っている奴がモテるという時代であった。ちなみに、1990年と現在は、人口は大体同じぐらい、実質GDPは1.3倍だが、20代人口が3/4に減り、自動車販売台数(バス、トラックを含む)が、778万台から478万台、つまり約40%減少しているという状況である。逆に言えば国内市場が40%縮小しても元気な自動車産業は偉い。 さて、彼らの意見を聞いていると、学生には、自動車を購入する、所有するという発想はない。友だちと旅行に行くときにはカーシェアリングを使うことはあるが、日常的に車で移動する習慣はないし、都会の交通インフラが便利になっているので、車で移動する必要性を感じないという訳である。講義が雨の日にあったらもう少し議論が変わったかもしれないが・・・ これまでは、1990年の話をすると割と何でそんなバカげた理由で車を買うのかという反応が多かったが、今回は一周回って、昔話としては理解できるという反応が多かった。1つ鋭い指摘だったのが、ステータスに対する認識が大きく変わったのではないかという指摘であった。その当時、車を持つ、スポーツカーを持っているということがステータスだったのではないか。それに対して今は、SNSでフォロアーが多いとか、ゲームの成績がステータスであり、車は映えず、そういう価値はないという指摘である。なるほど、そうだとしたら若者は車を買うわけないと深く納得した。 デートに必須とか、高いステータスを獲得するために必須のアイテムという幻想が失われてしまうと、どう考えても都会で車を所有する合理的な根拠はない。初期投資額、維持費、駐車場代が割りに合わない。都会は交通インフラが発達していて便利だし、速くて正確。自動車は移動時間も正確に読めない、交通事故のリスクが怖いといった意見も出た。昔は車があれば、通勤通学の時間も自分の空間があって、音楽やラジオが聴けて、電車の混雑が避けられるということだったが、電車の混雑度は若干は緩和され、スマホとイヤホンでそういった楽しみもバーチャル化されて実現されているのだろう。 かように、若者は車を買うことが全く眼中にないとすると、テレビでやっている山のような自動車のコマーシャルは何なのだと思ってしまう。あ、そもそも若者はテレビを見ないのか。この辺に、空間は同じ所に暮らしていたとしても、ライフスタイルに大きなジェネレーションギャップがあることに、改めて気付かされる。 学生の意見を聞いていると、彼らのライフスタイルはつくづくサービス社会に既に移行済みであると感じる。買い物はオンラインショッピングで、友だちと遊ぶのもオンラインゲーム、会話もLINE。その意味で外出する機会が減った。旅行のために車を使うことがあるが、頻度が低いのでカーシェアリングで充分。目的に合ったサイズの車を借りられるのでむしろ便利。キャンプに行ったりすることもあるが、それも身一つで行ってキャンプができたり、バーベキューができるサービスを利用する。つくづく、ものを所有せず、サービスを適切に選択して活用するライフスタイルの広がりを感じる。改めて1990年と今を比べてみると、時代は実際大きく変わっているし、まさに、諸富先生が言う「非物質主義的転回」(諸富徹: 「資本主義の新しい形」, 岩波書店, 2020)が身の回りで十二分に起きていると感じる。 とすると、筆者らは、脱大量生産・大量消費だ、サーキュラー・エコノミーだと、説教臭く言っているが、若者のライフスタイルは既にそうなっているのではないか。むしろ彼らを手本として、変わるべきは、筆者らの世代であり、おそらく、日本メーカーの体質、思考回路なのであろう。学生のレポートにも、「製造には強いが新たなコンテンツを生み出すイノベーションに弱いというままでは、近年コト消費を生み出し続けている海外企業に対し、競争力が低下する一方だと危惧されます。」とあった。 改めて思ったのは、社会は時間と共に大きく変わる、変えることができる、そこは確信をもって良いということである。しかし一方で、1990年と今を比べたとき、CO2排出量はほとんど減ってないし、資源消費量も多分ほとんど減ってない。若者のライフスタイルの産業部門を含めた日本全体のCO2排出、資源消費に対する影響力がまだ充分に大きくなく、今後は加速度的に削減が進むと信じることにしよう。